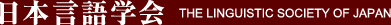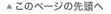第113回大会研究発表一覧《午前》
A会場
| 司会:荻野 綱男 | 日本語の「する」構文について | 横田 賢司 |
| 日本語の指示表現のタイプと推意 | 秋月 高太郎 |
| 司会:徳川 宗賢 | |
| 日本語の心理動詞と共起する「に」名詞句と「を」名詞句の特徴 | 板東 美智子 |
| 日本語のガ格とヲ格の非階層的付与について | 佐藤 直人 |
| 失文法患者の主格を表す「が」の産出状況に関係する意味的要因について | 藤田 郁代, 井原 浩子 |
B会場
| 司会:松村 一登 | |
| 非両立語・多項対立の反意関係 | 足立 公平 |
| 擬態語の意味のメカニズムについて | 小田 弘美 |
| 司会:湯川 恭敏 | |
| 英語の名詞転換動詞の比喩的意味拡張 | 谷脇 康子 |
| Dative Alternation and the Semantics of the 'give' Construction | 児玉 一宏 |
| 隠喩にみる言語の思考的機能 ―ウォーフの言語相対論の理論的展開― | 太田 智加子 |
C会場
| 司会:吉田 和彦 | |
| アイヌ語タライカ方言と北海道方言の間に見られる /r/ と /t/ の対応とその例外について | 高橋 靖以 |
| 述語の構造 ―日本語・韓国語・アイヌ語― | 村崎 恭子 |
| 司会:角田 太作 | |
| 中国語と英語の言語表現のイメージスキーマによる解釈について | 山崎 雅人 |
| 中国語の結果合成動詞の構造について | 沈 力 |
D会場
| 司会:早田 輝洋 | |
| 満州語文語の接尾辞 -ngge の用法について | 木村 滋雄 |
| 現代モンゴル語の過去の事実を指し得る動詞語尾について | 水野 正規 |
| 司会:庄垣内正弘 | |
| チュクチ語の名詞抱合について | 特 古 斯 |
| コモックス語のアプリカティブの接尾辞について | 渡辺 己 |
| ハイダ語スキドゲイト方言の代名詞について | 堀 博文 |
E会場
| 司会:熊本 裕 | |
| 古典アラビア語文法における jins(種)の概念 | 榮谷 温子 |
| 現代アラビア語のテクスト分析に基づく qad +“完了形”の機能について | 近藤 智子 |
| 司会:藪 司郎 | |
| アッカド語のいわゆる来辞法について | 森 若葉 |
| 古典シリア語における動詞の完了形と存在動詞 hwa との複合形式について | 楢崎 勝則 |
| 現代ロシア語副動詞 (converb) の談話的働き | 北上 光志 |
第113回大会研究発表一覧《午後》
A会場
| 司会:荻野 綱男 | |
| 「ため」の多義性の一側面: <目的>と<原因>の融合 | 金森 千恵 |
| 存在動詞「ある」と「いる」―PROCESS/RESULTをめぐって― | 高橋 純 |
| 司会:早田 輝洋 | |
| 「再帰中間構文」再考 | 今泉 志奈子 |
| 再帰形の logophoric な機能について | 杉浦 滋子 |
B会場
| 司会:坂本 勉 | |
| モダリティと条件文および理由文の交替について | 吉良 文孝 |
| 派生の経済性と wh 島効果における主語と目的語の非対称性 | 西前 明 |
| 司会:角田 太作 | |
| Carlson の存在論と tough 構文の解釈について | 三木 望 |
| 照合理論と縮約現象 | 鎌田 浩二 |
C会場
| 司会:村崎 恭子 | |
| 中国語陽谷方言の r 化について | 東ヶ崎 祐一 |
| 朝鮮語 [ATR] 母音調和と最適性理論 | 平野 日出征 |
| 司会:村崎 恭子 | |
| The Structure of mora nasal | 那須川 訓也 |
| 英単語の視覚認知における音韻処理 | 門田 修平 |
D会場
| 司会:田村 すず子 | |
| ブヌン語(南部地方)における場所の表現 | 野島 本泰 |
| インドネシア語の -nya と itu の前方指示機能の比較 | 内海 敦子 |
| 司会:庄垣内 正弘 | |
| インドネシア語の従属節中の di- 形動詞の主語の省略に関する談話・機能論的要因 |
安田 和彦 |
| Object Preposing | 中村 政徳 |
E会場
| 司会:藪 司郎 | |
| ハワイ語の he の統語的性質 | 塩谷 亨 |
| ムニャ語の音韻的諸特徴について | 池田 巧 |
| 司会:吉田 和彦 | |
| マリ語の連休修飾構造について | 松村 一登 |
| ヘレロ語動詞のアクセント | 湯川 恭敏 |