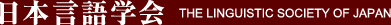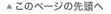古代日本語の係り結びコソ―その起源と構造―
新里瑠美子 (ジョージア工科大学)
古代沖縄語のス= siの係り結びと古代日本語のコ乙ソ乙=ko̠so̠の係り結びは,已然形で結ぶ強調表現であるところが類似するが,積極的に比較研究されることは少なかった.本稿においては,両者を比較し,日本祖語における原形を*ko̠#swo(指示詞の*コ乙+形式名詞の*ソ甲)と再構する.そして,有坂第一法則の適用で,甲類のswoが,先行する乙類のoに母音調和した結果,古代日本語では,ko̠so̠となったと仮説する.ソ甲の部分が甲類で,形式名詞であったとの見解は,従来の近称のコ乙+中称のソ乙との語源と相容れないが,その裏づけとして,(1)沖縄最古の辞書『混効験集』の知見,(2)西日本方言に痕跡を留める形式名詞のス・ソ,(3)機能論,文法化理論の観点からの論証を挙げる.更に,コ乙ソ乙(沖縄ス=si)とカ(沖縄ガ)の係り結びを対照させ,両者の結びがrealisとirrealis(古代日本語は多くが推量の助動詞-(a)m-)に対応する意味を認知論的に考察し,また指示詞から係助詞のようなfocus particleへの移行は世界の言語の文法化のデータにも合致する点を指摘する.
日本語の非対格動詞と敬語
本論文では,日本語の非対格動詞を伴った文における敬語現象を考察し,主語はVP内に留まるのではなく,顕在的に移動するが,直接Spec TPに移動する前にSpec νPに移動するということを提案する.日本語には二重敬語という現象があり,非対格動詞構文の一致現象を見ていくと,与格を伴った要素が謙譲語,主格名詞が尊敬語の一致を担っている.敬語の分析については,Boeckx and Niinuma(2004),Niinuma(2003)が論じたように,敬語を一致現象の一つのタイプだと仮定し,Agreeという操作によって説明可能であるとする.この仮定により,非対格動詞構文の主格名詞はSpec vPに移動するということを提案する.
この分析が正しければ,Miyagawa(1989)が考察した非対格動詞と非能格動詞における数量詞遊離の違いをBošković(2004)の分析に従って説明できるということを論じる.
関連性理論によるHoweverの分析
Blakemore(2002)は,関連性理論の立場から,副詞的連結詞howeverの意味論分析を行っており,howeverは次の2種類の制約を持つ手続的意味をコード化するものであるとしている.(1)howeverで
マークされた発話を解釈する際の,文脈効果の種類についての制約(具体的にはある想定の矛盾と削除)(2)その文脈効果が導かれるべき文脈についての,複雑で一部否定的な制約.
本稿では,このBlakemore(2002)の提案に対して,その代案となるよりシンプルな手続的考え方を提案し,その有効性を主張する.第1の制約はBlakemoreの(1)の制約と同一であるが,第2の制約は,先行する談話セグメントの明示的内容を肯定すると同時に,その肯定内容に対して,矛盾想定を推論的に結びつける,とする点で主張が異なる.
本稿の提案は,howeverとbutの交替可能性についての既知の制約に符合する.また,Blakemoreの提案と比較して,全体的なシンプルさ(アドホックな否定的条件をおく必要がなくなることなど)と,観察事実との一貫性という両方の点で勝れている.
獲得期音韻体系の類型論的特徴―形式・機能両面からの考察―
音韻の獲得段階にある幼児の音韻体系は,産出の「誤り」(逸脱発音)のパターンに基づいて類型化されることが多かった.このような類型化は,典型的な音韻発達を示す多くの幼児の音韻体系の記述には適切である.しかしながら,幼児の中には,例外的とされる逸脱発音を見せる例も存在し,このようなケースには,この種の類型化は対応することができない.またこの「典型」対「例外」の背後には,これまでほとんど関心を引くことがなかった,幼児の音韻知識を質的に区別する,機能的な特徴が潜んでいるのである.
本論考では,最適性理論に依拠した類型化を提案する.これは,形式面からの類型化であり,最適性理論の基本的な概念である,入力と出力,そして音韻制約のランキングの組み合わせに基づくものである.これらの三者が,例えば,入力は正常,出力は逸脱,ランキングは逸脱というように,「正常」か「逸脱」かいずれかであることにより,理論的には7種類のカテゴリーが可能となる.
この類型化により,これまでの逸脱発音のパターンのみではカバーできなかった,獲得期のすべての音韻体系が記述可能であるのみならず,上記の機能的な特徴も,この類型化と最適性理論の構成概念から直接導かれるのである.
述語の等位接続と日本語の句構造
本論文では,等位接続詞「そして」を用いた日本語の述語等位接続構造を考察し,とりわけ当該等位接続構造の左の被接続要素に,相反する理論的結論を導く2種類の文法現象が見られることを指摘する.はじめに,述語等位接続構造の左の被接続要素には,時制要素が現れることがないにもかかわらず,主格主語は現れうることを示す.これは,左の被接続要素が最大でもvPまでの投射であり,TPは含まないことを示唆する.そうだとすると,左の被接続要素内に移動先が存在しないから,日本語では,可視統語論における動詞や主格主語のTP領域への繰り上げが起こっていないことになる.その一方で,可視統語論での主語や動詞の繰り上げの存在を示す現象も左の被接続要素に現れる.これは明らかに左の被接続要素がTPまで投射されていることを意味する.当該述語等位接続構造をvPと分析してもTPと分析しても,相反する2種類の経験的事実を同時に説明することはできない.本論文では,最後にいくつかの問題解決の可能性を示唆する.