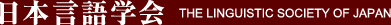日本語ノンヘデッド複合語における音素上の偏り 「ワープロ」,「あれこれ」,「めちゃくちゃ」の共通点について
本稿は日本語における外来複合語の短縮形(例:ポケモン),エコーワード(例:めちゃくちゃ)および対立語(例:白黒)といった3種類の2項からなるnon-headed複合語を対象に,これらの語の音韻構造,特に前項および後項における頭の音素の分布と頻度を統計的に検討する.その結果として,3種類の複合語の適格性は,各項の頭の音素の性質によって決定されるということを明らかにする.統計的に有意な最も際立った特徴として,ア行(つまりゼロ子音)で始まる要素は複合語の第2項として現れることが非常に少なく,カ行で始まる要素は第2項として最も現れやすいということが言える.本稿においては,これらの音素上の偏りは,知覚的および音韻的な要因に規定された音力階層によって説明され,またこのような複合語の音韻構成は機能的な動機付けによっていると主張する.
無標形の発現としてのアスリ諸語の重複
本稿は,独立に動機付けられた無標構造が新たな機能のために利用され,その姿を現すという意味の「無標形の発現」について論じる.この意味での無標形の発現は様々な言語現象に見られるが,本稿では重複における無標の韻律構造の発現に焦点を当て,それをアスリ諸語の重複を例に論じる.アスリ語派の言語には数種類の重複があり,そのうちのいくつかは韻律・形態論的に一見特異に見える性質を持っている.本稿は,そうした一見特異な重複が,通言語的によく見られる重複と同じように,上で述べた意味での無標形の発現現象として説明できることを示す.また,今後の研究の方向性として,そもそもなぜ言語にはそうした無標形の発現がよく見られるのかという問題を提起し,その背後にあると思われる一般的な制約の探究の必要性と重要性を指摘する.
素性階層理論と音声素性 ―日本語の有声化とコーダ鼻音化についての試み―
日本語の有声同化及びそれに関連する有声コーダ鼻音化の現象を説明する企てを通して,空力素性階層理論の修正を提案し,それを通じて素性階層理論と音声素性との関係について注意する.まず,有声同化現象を説明するのに,素性階層理論では,有声無声の別に対応する節点をたてず,それに代えて「清濁」の別に対応する節点をたて,流音・半母音は清,鼻音は濁とする.コーダ鼻音化は,射影反転という概念のもとで,中和現象として素性階層理論的に自然に説明されることを示す.このような考察を通じて,音声素性は,音韻論と発声機構との境界条件の表現に必要であるにしても,素性階層理論本体の構成要素ではない,という提案をする.
Three Types of Imperatives: Japanese/English Imperatives and the Scale of Potential/Actual-Type
The purpose of this study is to consider imperatives in Japanese and English from the perspective of general linguistics. The idea that imperatives can have a negative implication has been repeatedly exploited to classify them. As far as English imperatives are concerned, this criterion may be necessary and sufficient. They can thereby be divided into two groups: imperatives that carry negative implications and those that do not. I will demonstrate, however, that this does not hold true for Japanese imperatives. As evidence for this, I will discuss the compatibility of the Japanese auxiliary verb miro with imperatives. It is claimed that imperatives have at least three basic types, which are distinguished by different degrees of compatibility with the verb in question: optional, obligatory and unacceptable. To give a principled account of this fact, I propose a scale of the propositional content of imperatives, which has two polar opposites: potential-type and actual-type. On this scale, imperatives are classified according to whether they rely on the speaker's direct experience. Not only does the proposed scale allow us to explain different degrees of compatibility of miro, but it can also offer several refinements to existing knowledge about imperatives. Since imperatives, whether affirmative or negative, are located somewhere on the scale, no assumption of the so-called idiosyncrasy of negative imperatives is needed in the present paper. The discrepancy in the scale between Japanese and English imperatives in turn makes their typological differences clear.
A Comparative Study of Haya, Ankole, and Tooro Tone Systems in Connection with Tone Loss in Tooro
In western Uganda, some closely related Bantu languages such as Ankole, Kiga, Tooro and Nyoro are spoken. These languages are sometimes referred to as the Runyakitara language group. This group also includes Haya, a Tanzanian language which is spoken just to the south of Ankole. When we look at the tone systems of these languages, there are some striking differences. The most obvious difference is that, whereas Haya, and also Ankole to a certain extent, retain a relatively old tonal system (Kiga and Nyoro data lacking), in which the disyllabic -HL, -LH and -LL noun stems are differentiated, Tooro, which is spoken to the north of Ankole, has almost completely lost the original tonal system: the penultimate syllable of the word is always high-pitched in isolation. The author tries to explain how the Tooro system, which phonologically lacks tone, has come into being, by analyzing the differences which exist between the Haya system and the Ankole system. The Haya system is the oldest among these languages, and the Ankole system can be characterized as moving from the Haya system toward the Tooro system. We find in Ankole itself some signs of change, such as non-clear distinction of the underlying -HL and -LH patterns, and high tone loss in a number of words.
日本文の処理におけるスクランブル効果の諸問題 ―Koizumi and Tamaoka(2004)に対するMiyamoto and Nakamura(2005)のコメントへの回答
小泉政利 (東北大学)
Koizumi and Tamaoka(2004,以下KT)の実験結果に対して,Miyamoto and Nakamura(2005,以下MN)が寄せたコメントについて,3つの視点から回答した.第1に,KTの実験条件ではMNが指摘しているような再解析が起こらないことを示唆する経験的証拠を提示し,少なくともKTの実験においては,統語構造の複雑さが文正誤判断課題の反応時間と関係するという仮定が成り立つことを再確認した。第2に,頻度について,語彙,統語,共起の3種類があることを説明した.語彙頻度についてはKT(2004)の実験では比較条件で一様であるため,影響がない.統語頻度については,KTが使用した実験刺激の頻度をMNが示している(MN, Table 2, p. 121)が,これが実験統制に用いられる通常の方法であるにもかかわらず,結果を不十分としているのは不適切な議論であることを指摘した.MNの文完成課題については,興味深い結果を得ているものの,オフラインの結果であるため,それを支持するためのオンラインの実験が必要であろう.共起頻度については,今後の研究を待つことになろう.第3に,文正誤判断課題と自己制御読みに関して,MN自身も指摘しているように,自己制御読みについては複雑な文でない限り有意なスクランブル効果が観察されていない.本稿では,近年行われた文正誤判断課題の実験がスクランブル効果を一貫して観察していることを示した.その上で,自己制御読み実験では,キー押しのための運動が文処理に影響すること,読みのために与えられる課題が「二重課題法」のように機能して,文処理以外に過度な記憶負荷をかけていることなどを指摘した.
A Numeral Denoting ‘One’ in Ainu
This paper attempts to show that in Ainu the number ‘one’ can be referred to by the proclitic ar which means ‘one of a pair’ (as-siki ← ar-siki ‘his eye’) or ‘half’ (ar-kewtemu ‘half of his heart’), and also functions as an intensifier (ar teynep ‘a true baby’). Although ar is qualified to be a numeral semantically, it has not been treated as such in traditional descriptions.
It is arguable that in general a numeral denoting ‘one’ can be derived from the concept of ‘a half of two’ and that a typical case of illustrating this process is observed in Ainu.